債務葬式費用の範囲(相続財産から控除できるもの)
2024-10-18
カテゴリ:税務会計,相続税法
相続税の計算方法
相続税の計算方法は大雑把に言えばプラスの財産からマイナスの財産を引いた差額分が相続税の課税の対象となります。
そこから法定相続人の数に応じて基礎控除額が算定され、保有する宅地によっては小規模宅地等の減額を受けることができたり、法定相続人に障害者や未成年者がいる場合には税額控除の対象となります。
相続税の計算は非常に複雑で、基本的には財産評価基本通達に基づき計算を行いますが、例えば土地を一つとってもマニュアル通りの形のものは無く、財産評価をする上では非常に頭を悩ませるところでもあります。
相続税の計算は非常に複雑なものですが、今回はその中でも”マイナスの財産”である債務控除について記事にしていきたいと思います。
債務について
「債務」とはその名の通り亡くなられた被相続人が残したマイナスの財産です。
ですのでまず、債務控除として認められるものを列挙します。
ですのでまず、債務控除として認められるものを列挙します。
■借入金
金融機関などの第三者からの借入金については債務控除として控除が可能です、また、金融機関以外の者からの借入金についてはそれ相応の客観的な証拠(契約書など)が必要になります。
例えば生前被相続人に生活費を援助していたようなケース、これは借入金ではなく、被相続人への贈与になろうかと思います。
例えば生前被相続人が家の修理をするためにお金が足りず貸したような場合、これは客観的な証拠があれば債務控除の余地はあろうかと思います。
同じお金を渡すにしろ、債務控除の対象にするには後日検証可能な証拠書類を残すことが大事です。
■未納税金、未納保険料など
固定資産税や住民税などの税金、後期高齢者医療保険や介護保険の未納分です、賦課期日時点の持ち主に対し課税がされる税金については賦課期日後の未納分については債務控除が可能です。
(参考)
固定資産税、住民税の賦課期日:1月1日時点
■未払医療費、介護サービス費用など
被相続人に係る医療費、介護サービス費用など被相続人の死後に相続人等が支払ったものについては債務控除の対象となります。
※準確定申告がある場合、医療費控除と債務控除の同時適用ができます(所得税は所得課税、相続税は財産課税で課税の考え方が異なるため)。
■その他
水道光熱費、電気代、電話代、不動産オーナーであれば預かり敷金などその他被相続人に帰属するものの未納額については債務控除が可能となります。
債務控除については細かく聞き込みをしながら探す必要があるため、とりあえずは手元の領収証や請求書などを捨てずにとっておくことをおすすめします。
葬式費用について
葬儀にかかる費用は様々でありますが、国税庁の相続税基本通達にて葬式費用に該当するものとしないものとを示しております。
■葬式費用として控除できるもの
・通夜や告別式などの主に葬儀会社に支払った費用
・通夜振る舞いや精進落としなどの通夜・告別式に係る飲食費用
・葬儀手伝い者に対するお礼代
・寺などに支払ったお布施、戒名料など
・火葬、埋葬、納骨に係る費用
・死亡診断書発行費用
などです。
※寺などは領収証を発行しないことがほとんどですので「支払日」「相手先」「金額」のメモを残し、後日立証できるようにしておくのが良いと思います。
※葬儀手伝い者に対するお礼を現金で支払う場合も同様に「支払日」、「相手先」、「金額」のメモを残し、また、通常の相場から著しく乖離しない金額(おおよそ5,000円程度)が望ましいです。
■葬式費用として控除できないもの
・香典返し
→香典が課税されないため
・墓石、墓地などの購入費用
→葬儀との因果関係がないため
・初七日、四十九日、一周忌などの法要費用
→被相続人を供養するための費用ではありますが、葬式費用として認められるのは通夜、告別式までです。区切らなければキリがなくなります。
まとめ
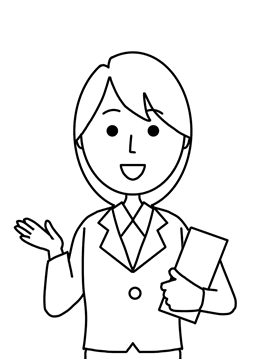
債務については被相続人のマイナスの財産ではありますが、当の本人はこの世にいないため潜在的なところまではわかりかねる部分もあるのかも知れません。
生前に色々と話しを聞きながら、被相続人のことを十分理解することが大事です。
ちなみに債務控除については税務当局から見ればマイナスの財産であり、相続税額のマイナス要因であるため、見逃したものはそのままとなってしまうケースがほとんどですので、知りうる範囲内での調べ込みと証拠書類を残すことが大事です。
葬式費用についても証拠を残すことが大事です。
特に住職に支払ったもの、手伝ってくれた人に支払ったものなどは後日曖昧になってしまいがちです。
被相続人を供養する意味でも悲しみの最中ではありますが、後日思い出せる程度のメモは必要かと思います。
